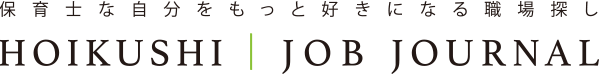ISSUES
いろんな園の新着情報

森〜センス・オブ・ワンダー〜見て、感じて、そしてただひたすら驚くこと【前編】
(本記事はNPO法人さくらの森・親子サポートネットの10周年記念誌「つなぐ さくらの森10年」の記事をHOIKUSHI JOB JOURNAL用に一部編集して掲載しています)
NPO法人さくらの森・親子サポートネット

座談会参加メンバー
左から(後列)宮元さん、尾登さん、伊知地さん、山川さん、山﨑さん、石川さん(前列)井上さん、外村さん、菊地さん、小林美緒さん、小林美津子さん、谷合さん/撮影&記録:若狭さん
(本文中、敬称略)
外で遊べない日々から、森に行けた!

伊知地:保育園の立ち上げに向けて準備を進めていたとき、周辺は交通量も少なくとても静かで、子どもたちが歩いて行ける距離に自然豊かな「泉の森」があると知って、この場所で保育ができることに大きな可能性を感じました。
宮元:そうですね。前の職場でも近くに森があって、子どもたちとよく遊んでいた経験があったので、「自然の中で育つ」ということを大切にしたいという思いが強くありました。泉の森が近くにあるならそれが実現できるかも、と思って。でも、そこから具体的にどうしていくかまでは話が及んでいなかったんです。
菊地:子どもとどんなふうに関わるのか、何を準備していくのか、といったことはみんなでたくさん話しましたね。
伊知地:いろんな課題を抱えたままのスタートでしたが、無事に保育園が開園した直後に東日本大震災と原発事故が起きました。目に見えない放射能の影響に不安があって、3月は外遊びを控えるという選択をしました。
宮元:余震が続き、放射線の心配もあって外には出られなかったんですが、子どもたちは保育室の中であちこち移動しながら、思い思いに遊びを楽しんでいたのが印象的でした。
伊知地:そういった不安定な状況の中でしたが、4月8日から徐々に日常を取り戻していこうということで、まずは幼児クラスから森へ出かけるようになりました。
菊地:外に出るときも、緊急地震速報が何度も鳴っていて、いつも警戒していたのを覚えています。でも、2階の何もない部屋でぐるぐる走っていたのが日常だったから、森に行けたことがとても感動的でした。

山川:秋頃からは、本格的に森や公園を探索するようになりましたよね。
小林美津子:幼児クラスから「泉の森ってこんなところだよ」という情報が届いていたので、2年目から一時預かり(通称:いずみさん)を担当するようになって、私も森に足を運ぶようになりました。歩くのが好きな子が多かったので、1週間ほどで森を一周するコースを1時間くらいで歩けるようになりましたよ。1歳の小さな子どもたちも、ちゃんと大人についてきていました。
伊知地:あの斜面も登ってましたよね?
小林美津子:そうなんです。最初は「あの斜面、登って大丈夫かな?」と不安もあったんです。でもある日、一般の人がその斜面を降りてくるのを見て、「あ、登ってもいいんだ」と。それで一気に挑戦する気持ちが湧いてきました。
山川:まだよちよち歩きの子たちも、大人と一緒に斜面を登っていて、その姿に驚きました。転んだらどうしようって思ったんですが、子どもたちは本当に楽しそうで。私が担任をしていたクラスの子は、最初は森で遊ぶことができず、ただ通り過ぎる場所だったんです。でも、いずみさんたちの様子を見ているうちに、「やってみたい」という気持ちが芽生えて。いつの間にかスピードもついて、いろんな技も覚えていきました。
小林美津子:秋になると斜面には折れた枝やどんぐりがたくさん落ちていて、それを拾いながら登る子もいたんですよ。そうしているうちに、ある日斜面の上に子どもたちの“秘密基地”が出来上がっていて。拾った枝をうまく活用していたんです。

宮元:泉の森は散歩に来る人も多いので、全体としては自由に遊べる場所ではないんですよね。だから、人があまり来ないような場所を探して、そこでたっぷり遊びました。「アリ地獄」と名付けた大きな窪地を見つけた時は、大はしゃぎでした。
伊知地:初期の頃は、みんな手探りで、自分の経験をもとに森での活動を模索していたんですよね。
山川:小林さんの遊び方をそばで見ながら、「あ、こういう風にすればいいのか」と少しずつ学んでいきました。
小林美津子:私自身が自然に囲まれて育ったので、泉の森に初めて行ったとき、子どもの頃の感覚が一気に蘇ってきたんです。見ただけで「あれもできる」「これもできそう」とどんどんイメージが浮かんできて、毎回行くのが本当に楽しかったです。
伊知地:なるほど、それは大きいですね。体で覚えている感覚があるというのは強みです。だからこそ、子どもたちが自然の中で遊ぶことで“センス・オブ・ワンダー”を育てていくことが大切なんですよね。
大人がおもしろさに気づいていく!

伊知地:もっと子どもたちと一緒に森で深く遊べたらと思い、ある時期、自然環境の保全に携わる方や森に詳しい専門家をお招きする機会がありました。
山川:そうでしたね。自然素材を使った笛作りを教えてもらったり、カブトムシのいる場所を一緒に探したりしました。目を閉じて香りを感じたり、手で触って葉っぱを当てたりと、五感を使った遊び方をたくさん教わりました。
尾登:その方たちは小さな子どもの声にもよく耳を傾けてくれて、自然な距離感でそばにいてくれるんですよね。植物や虫の名前、それに森での遊び方などもいろいろ教えてもらいました。
山川:泉の森に多くあるアオキの葉っぱも、「これで字が書けるよ」とか、子どもにもわかりやすい方法で教えてくれて。そうやって自然に遊びを覚えていったんだと思います。
石川:山川さんが専門家と一緒に遊んでいる姿、ほんとに嬉しそうなんですよ。それを得意げに子どもたちに伝えてるのを見ると、こっちも元気をもらえるんです。自然って、大人の心も大きく揺さぶる力がありますよね。他の人がそういう瞬間に出会ってるのを見るのも、また楽しいんです。
伊知地:専門家の方々と関わることで、大人たちも少しずつ森を楽しめるようになって、子どもにその面白さが伝わるようになったと感じます。それで、子どもたちの森へのまなざしも変わってきて。さくらの森保育園では、自然との関わりが中心になっていったんですが、あとから入ってきた皆さんはどう感じましたか?
尾登:私は入ってすぐ森に行って、まず驚きました。1歳の子たちが斜面を登ったり、丸太の上を歩いたりしていて。2人の保育士で8人を見ている状況で、にぎやかで大変そうだなって。でも他の園では1歳児ってようやく散歩に出かけるくらいだから、この保育はかなりチャレンジングだなって感じました。

伊知地:衝撃を受けつつも、すぐに「いいな」と思ってくれたんじゃない?
尾登:確かにそう思いましたね。最初は滑ったり転んだりしながら登っていたんですが、子どもたちが自分で道を見つけていくのが分かってきて。この子はこう進むからここで支えようとか、この子は一気に行っちゃうからこの枝に気をつけようって、観察しながら対応していきました。
石川:私、自然の中で育ったはずなのに、虫が本当に苦手で、肌も弱くて植物にも反応してしまうので、正直森が怖かったんです。でも、子どもたちと一緒に調べたり、やってみたりするうちに、気づけば自然の中で夢中になってる自分がいて。森での経験が、日常生活にも深く影響するんだなと実感しました。
小林美緒:実習で来た時に驚きました。0歳児が砂の上を歩いて、4歳児が保育士を追いかけて森の中を駆けまわる。「ここって、こんなに森で遊ぶんだ!」って感動しました。虫が得意じゃない私でも、大人が楽しむことが大事だってわかってから森が楽しくなりました。「この虫なに?」「わかんないけど見てみよう」っていうやりとりが自然にできるようになってきて。
山﨑:私は虫より怪我が怖かったんです。枝につまずいたり、転んでおでこをぶつけたり。でも、そういう子どもたちも体の使い方が上達して、どんどん遊べるようになっていって。木にロープを結んでブランコを作ったり、宝物を隠して次の日にまた探したり、「続きがしたい」と子どもから声が出るようになってきました。私自身も一緒に楽しみながら変わっていった感じです。

谷合:私ははじめの頃、森の湿った匂いとかが苦手で抵抗があったんです。でも、たくましく遊ぶ子どもたちの姿を見ているうちに、気づけば自然に楽しめるようになっていました。2年間別の保育園に行ってたんですけど、そこの子どもたちは遊具がないと遊べなかった。でもこの園の子たちは、森に着いたらバギーを早く降りたがって、自分でやりたいことを見つけて動いてる。それが本当に素敵だなって思います。
外村:私、もともと保育園での仕事経験がなかったので、こんなに森で過ごすなんて驚きました。虫も苦手でしたが、子どもたちが本当に楽しんでいるのを見て、「これは何?」って一緒に調べたりしているうちに、抜け殻なら触れるようになったり、ダンゴムシを持てたり。少しずつ子どもたちと一緒に自然を楽しむ力を育てていっているところです。
井上:私も、最初は森で保育できることが嬉しくて。前にいた園では園庭遊びが中心で、週に一度近所の公園に行くくらいでした。自然の中で子どもと過ごしたいと思っていたので、ここに来て本当に感動しました。ただ、最初のうちは危ない場所の把握にすごく神経を使いましたね。転ぶリスクを見守る場所と、池の柵みたいに絶対に超えさせたくないラインがあるので。そういった感覚がつかめてくると、空を見上げて葉っぱが揺れているのに気づいたり、子どもの目が輝いた瞬間に立ち会えたりして、すごく幸せな気持ちになります。
菊地:もし普通の会社勤めをしていたら、こんな体験できなかったよねってよく話します。小さな虫に気づいて感動したり、毎日が特別に感じられる。ほんと、幸せな仕事だねって、井上さんともよく言い合ってるんですよ。
(後編に続く)
▼「さくらの森保育園」の情報はこちら