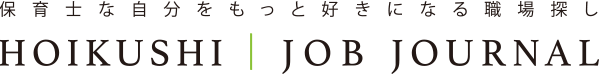ISSUES
いろんな園の新着情報

森〜センス・オブ・ワンダー〜見て、感じて、そしてただひたすら驚くこと【後編】
NPO法人さくらの森・親子サポートネット

座談会参加メンバー
左から(後列)宮元さん、尾登さん、伊知地さん、山川さん、山﨑さん、石川さん(前列)井上さん、外村さん、菊地さん、小林美緒さん、小林美津子さん、谷合さん/撮影&記録:若狭さん
(本文中、敬称略)
子どもの「なぜ?」「どうして?」から続く物語

伊知地:意外なことに、実は虫が苦手な人って本当に多いんですよね。しかも、森の中にはケガのリスクもあって。でも、子どもたちの「やってみたい!」という気持ちに引っ張られていくうちに、大人の方が「おもしろい!」と感じるようになる。その流れがはっきり見えてきました。最近では、子どもたちの関心を出発点にして、そこから活動を発展させていくことが増えてきています。
山川:「ザリガニ釣り」がまさにそうでしたね。水車のそばにある石段でザリガニを見つけて、私が素手で捕まえたんです。それがきっかけで、「自分も釣ってみたい!」って子どもたちの気持ちが一気に高まり、自分たちで釣り竿を作ろうということになって。お気に入りの木の枝にひもをつけて挑戦したんですが、結局その日は1匹も釣れなくて。その後、「どうして釣れなかったのかな?」とみんなで考えました。川の中をバシャバシャ歩いたから驚いて逃げたのかも、とか「暑い日の方がザリガニは活発に動くんだよ」っていう話が出てきたり。おうちでさらに調べてきた子もいて、どんどん学びが広がっていきました。
石川:「キクラゲ」の話も印象的でした。キノコが大好きな4歳児がいて、森の中で枝にたくさんくっついているぶよぶよの物体を見つけたんです。それが専門家に「キクラゲだよ。食べられるよ」と教えてもらってから、子どもたちの探究心に火がついて。朽ち木を見かけるたびに近づいて調べるようになり、「本物のキクラゲを食べてみたい!」という流れに。生活クラブで買った乾燥キクラゲを戻して、実際にみんなで触ってみたら「これ見たことある!」ってなって、普段は食べない子も「おかわりちょうだい!」と嬉しそうに食べていました。

井上:「ジャコウアゲハのさなぎ」の観察も面白い展開でした。以前に写真で見て興味を持った子がいて、水車の近くで見つけたさなぎを毎日見に行くようになったんです。それがきっかけで、虫に興味を示す子が増えてきて、今まで図鑑を開かなかった子が虫の本を真剣に見ていたり。子どもたちの関心をもっと深めるにはどうすればいいか、保育者同士で話し合って、蝶の種類を調べて掲示したり、絵本を用意したりしました。園でさなぎの様子を見せたいと飼育を検討しましたが、餌となる植物が特定の場所にしか生えていないため断念し、自然の中で観察を続けることに決めました。
石川:森での飼育ごっこがきっかけで、飼育活動にも発展したんです。ダンゴムシの家づくりから始まり、ある日子どもが森で見つけた幼虫に「にょっき」と名前をつけて連れて帰りました。調べるとキアゲハの幼虫らしかったので、餌の葉を用意しましたが、まったく食べなくて。これでは生きられないと判断して森に戻しました。ところが後日、ある子が「あれ、ジャコウアゲハだったんじゃない?」と図鑑で確認し、それをきっかけに「じゃあ蚕を飼ってみよう!」という流れに。みんなで2か月以上かけて飼育し、脱皮から繭、成虫になるまでを見届けました。名前は「プリンセスちゃん」。亡くなった時にはお墓を作り、「お腹がすかないようにご飯もあげよう」と話しながら埋葬していた子どもたちの姿に、命を大切に思う気持ちがしっかり育っていると感じました。
なぜ森に行くの?

伊知地:森の不整地を歩くということは、自然とバランスを取ったり足元を意識したりするので、体幹を育てることにもつながるんですよね。同じ場所に何度も通う体験が、子どもたちの感性や思考にどう影響するのかも面白いところです。「なぜ森に行くのか」を、ちゃんと言葉にしていきたいと感じています。
井上:森の魅力って、ちょうどいい刺激があることと、色や形、音や匂い、手触りなどが調和していることだと思います。天候や季節でその表情が変わるからこそ、子どもたちは「ちょっとした違い」に敏感になっていく気がしていて。それに、子ども自身が興味や成長段階に合わせて自由に選べる環境でもあるんですよね。走ったり登ったりが好きな子もいれば、ままごとを始める子、虫をじっと観察する子もいて。自分の「好き」がそのまま活動になるのが素敵です。
伊知地:本当に、すべての子どもに開かれた場所ですよね。
井上:今の社会って、思い切り体を使って遊べる場が限られているけれど、森では思いっきり走ったり大声を出したり、地面に触れて草を引っこ抜いたり、泥だらけになるような経験ができる。そういう五感を通した体験が、子どもたちの中にしっかり根を下ろしていくと思うんです。
石川:同じ場所に何度も行きながら、行きたいという気持ちを継続するって、実は小さい子には難しいことだと思うんです。でも、森には毎日変化があるから、子どもたちの好奇心を飽きさせないんですよね。森はいつでも何かしら答えてくれる。その中で「もっと知りたい」「もっとやりたい」という気持ちが育っていくのは、とても価値があるなと。
井上:自然は反応してくれる存在ですよね。水たまりに触れたら波紋が広がって、足を入れたら跳ね返ってくる。おもちゃのように完成されたものとは違って、森の素材は想像次第で何にでもなれる。葉っぱは器にも船にもなるし、棒が箸や剣になることもある。色も、人工物と違って複雑で微妙な変化があり、空や雲、木々の色合いなど、そういう多様な世界に触れることができるのは、特に乳幼児期にこそ大切なことだと思います。

小林:確かに、いいことばかりじゃなくて、「うわっ、危ないかも」とか「ちょっと不便だな」と感じる瞬間もある。でも、そういった経験も含めて、子どもたちの生きる力になっていくんですよね。
伊知地:ケガのリスクをゼロにはできないけど、そういう体験の先にある成長を、保護者にどう伝えていくかはまだまだ課題ですね。
宮元:保護者にはじめに「森で遊びます」と言うと、みんな「いいですね」って言ってくれるんです。でも、実際に泥だらけの服やすり傷が増えると、「また洗濯物が…」みたいな声も出てきます。特に女の子のお母さんは「かわいい服が着られない」って気にされる方もいて。
伊知地:でも最近は、ドキュメンテーションで日々の様子をタイムリーに共有できているので、少しずつ保護者の意識も変わってきているように感じますね。
石川:例えばセミが好きな子の話が伝わっていると、毎日抜け殻を持って帰っても「また?」とならずに、「あの子、夢中なんですね」と理解してもらえたり。虫が苦手な家庭でも、うちの子が触れるようになったことに感動してくれるんです。
菊地:洗濯物が増えますって4月にお伝えすると、最初はびっくりされるんですけど、しばらくすると「まぁ、いつものことですね」って、受け止め方が変わってくるのがわかります。
伊知地:休日に家族で泉の森に行って、子どもが道案内してるなんて話もよく聞くようになりましたね。保護者の方が「こんなところまで来るんだ!」って驚くこともあるみたいで。子どもが本当に森を楽しんでる証拠ですよね。
森のナラ枯れ

伊知地:今や森は、ただの通り道じゃなく、目的地になってる。けれど泉の森も以前とは変わってきましたね。ナラ枯れが進んでいて、立ち入り禁止区域も増えてきた。中には毒性の強いカエンダケが出る場所もあります。これは泉の森だけの話じゃなくて、全国の都市近郊の森でも起きていること。気候変動や里山の循環が途絶えたことが影響してるようです。
石川:今年は特に匂いがきつくて、「この森も終わりが近いのかな」と感じる瞬間があるんです。バーベキュー場周辺は酸っぱいような異臭が強くて近寄れないほどで。セミやカブトムシが集まる木なのに、子どもたちでさえ「くさい」って言ってます。

伊知地:年長くらいになったら、そういう森の変化を伝えてもいいかもしれないですね。
石川:「どうしてこの木が枯れちゃったのか」とか、子どもたちと一緒に考えることもできそうです。
井上:そういう経験が、将来「自然を守りたい」という気持ちにつながるんじゃないかと。泉の森で遊んだ記憶があるからこそ、大人になった時に何かしたいと思ってくれるかもしれない。今、その小さな“種”を蒔いているところなんだと思います。
伊知地:本当にそうですね。地球環境の状況は待ったなし。でも、そこに目を向ける力を持った子どもたちが育ってくれたら。
“センス・オブ・ワンダー”――自然の神秘や不思議さに気づき、心を揺さぶられる感性。それを育てる日々が、子どもたちの未来の土台になっていく。泉の森は、その原点のひとつになっています。
(前編はこちら)
▼「さくらの森保育園」の情報はこちら